ラッカーとポリウレタンの違いは硬化方法の違いから生まれる
前回、ラッカー塗装とポリウレタン塗装の特徴と違いをまとめました。
ざっくりいうと「 音や鳴りは良いけどデリケートで高いラッカー塗装 」と「 音質の面では不利だけどすごく扱いやすいポリウレタン塗装 」。
これらの違いは、両者の物質としての性質の差と塗膜の硬化方法によるものです。
今回はなぜそういった違いが出るかを解説します。
(前回記事は下記リンクよりどうぞ)
性質の違いと硬化方法
ギター・ベースのラッカー塗装では一般的にニトロセルロースラッカーが使用されます。
ニトロセルロースラッカーはラックカイガラムシの分泌液を使った天然の物質。
一方、ポリ系の塗装では人工素材のポリエステルやポリウレタン、いわゆるPU樹脂を使用します。
実際に塗装するときにはどちらもシンナーで薄めてスプレーガンで吹き付ける方法をとりますが、硬化の仕方が全然違います。
ラッカーの塗装方法と硬化
ラッカー塗装はニトロセルラッカーをシンナーなど溶剤で溶き、スプレーガンで吹き付けて塗装します。
(スプレーガン=デカいエアブラシみたいなもの)
乾燥工程でシンナーを揮発させ、残ったニトロセルラッカー塗膜となるのがラッカー塗装の硬化方法です。
塗装は最終的に削って平面を出す → 磨いてツヤを出す工程を経て仕上げます。
このときの平面出しと研磨で薄くなる分、ある程度塗膜に厚みを持たせる必要があります。
しかしラッカー塗装は一度に吹き付けられる量が少なく、厚みを出すのに時間がかかります。一度に厚く吹き付けると内側のシンナーが抜けきれず、硬化不良を起こしてしまうのです。
そのため 薄く吹き付ける → 少し乾燥させる → 薄く吹き付ける → 少し乾燥させる…… と何度も繰り返して塗装していきます。
また、塗膜を削って磨く作業前の最終乾燥に非常に時間がかかります。べちょべちょの状態では触れないので、硬化するまで乾燥させる必要があるのです。
ラッカー塗装は非常に手間と時間がかかる生産性の悪い塗装方法。ラッカー仕様のギター・ベースの値段が高くなる原因です。
なお、ラッカー塗装のギター・ベースは完成後も塗膜に残ったシンナーが徐々に揮発して痩せて薄くなっていきます。
全く同じ厚みに仕上げたラッカー塗装とポリウレタン塗装のギターがあったとしても、ラッカー塗装はだんだんと塗装が痩せて薄くなっていきます。
シンナーが抜けた分塗膜が縮んで薄くなるので、ラッカーはギター・ベース本体の振動を阻害しない=鳴りがよくなる特性があるのです。
これが「 ラッカー塗装の方が音が良い 」といわれる所以です。
また、シンナーが抜けるにつれて塗膜の硬度があがりキズや打痕にも強くなっていきます。
ただし、塗膜が痩せて硬くなるにつれて塗膜の柔軟性が失われるため、ぶつけたときにパリッと割れてしまったり、乾燥によってウェザーチェックなどひび割れが入りやすくなっていきます。
ラッカー塗装の特性上、こういった経年変化、悪い言い方をすれば経年劣化とはうまく付き合っていくしかありません。
むしろ、経年変化によって増していくビンテージとしての風格を喜ぶ方も多くいらっしゃいます。
ポリウレタン、ポリエステルの塗装方法と硬化
ポリウレタン、ポリエステルなどポリ系の塗装は、複数の薬液を混ぜて塗料を作りシンナーで薄めてスプレーガンで吹き付ける方法で塗装します。
が、シンナーは揮発で硬化させるためではなく、あくまでもスプレーで吹き付けやすいよう薄めるだけの役割。
実際には混ぜた二つの薬液が化学的に反応することで硬化しています。硬化が早く、乾燥までにさして時間がかかりません。
そして一度に重ねられる塗膜の厚みががラッカー塗装よりも厚いため、短時間で塗装を仕上げることが可能です。
ラッカーのように経年変化によりひび割れるなどの劣化が少ないのも特徴。
手間や時間がかからず生産性が高いため、ラッカー塗装よりもギター・ベースの価格を抑えられる点もポリウレタン塗装の大きなメリットです。
まとめ:ラッカーとポリ系塗装のの違いは硬化の仕方から生まれる
- ラッカー塗装はシンナーの揮発によって徐々に硬化する性質を持ち、完全硬化まではかなり時間がかかる。
- ポリウレタン塗装は混ぜた液剤が反応することで硬化する性質を持ち、硬化が早い。
ラッカー塗装やポリ系以外にもオイルフィニッシュやシェラック塗装など、ギターやベース、ウクレレなどで使われる塗装方法については別途個別に解説しています。
ぜひ併せてご覧ください。














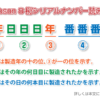

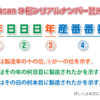






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)